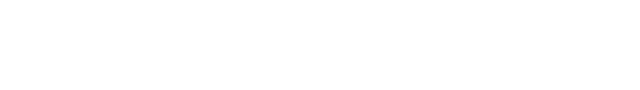適応障害の治し方は?うつ病との違いや治療法
適応障害は、特定の環境や出来事で生じたストレスに適応しきれず、心身に不調をきたす疾患です。
仕事や人間関係など日常的な場面が原因となり、突然働くのが怖いと感じることもありますが、特殊な症状ではなく、誰でもなる可能性があるものです。
うつ病と混同されることが多いですが、適応障害とは明確な違いがあります。
この記事では、適応障害の基本的な特徴や症状、治し方、回復までのステップなどについて紹介します。自分に合った対処法を知るための参考になさってください。
適応障害とは
適応障害は、特定のストレスに対して心身がうまく対応できなくなり、精神的・身体的な不調が現れる病気です。
ここでは、適応障害の基本的な特徴や、うつ病との違いについて紹介します。
適応障害の概要
適応障害は、特定の環境において強いストレスを受けた際に発症することが多い症状です。主に以下のような症状が見られます。
- 不安、気分の落ち込み
- 動悸
- 息苦しさ
- 食欲不振
- 頭痛 など
ストレスの原因が明確であることが特徴で、原因から離れると症状が改善することも少なくありません。
適応障害は誰にでも起こりうる可能性があり、決して特別なものではありません。早期に気づき、適切な対処を行うことで回復を目指せる疾患です。
うつ病との違い
適応障害とうつ病は似た症状を示すことがあるため、区別が難しい場合もあります。しかし、それぞれには以下のようないくつかの明確な違いがあります。
| 病名 | 特徴 |
|---|---|
| 適応障害 |
|
| うつ病 |
|
また、適応障害では比較的早期に改善する可能性がありますが、うつ病では長期的な治療が必要となることが多いです。
適応障害の症状
適応障害では、心や体にさまざまな不調が現れるため、本人だけでなく周囲の人も異変に気づくケースがあります。
ここでは、身体的・精神的・行動面の3つに分けて、適応障害に見られる代表的な症状を紹介します。
身体的な症状
適応障害では、精神的なストレスが身体に影響を与えることがあります。身体症状は決して軽視できない重要なサインです。具体的には以下のような症状が代表的です。
- 倦怠感
- 頭痛
- めまい
- 胃痛 など
このような症状は、自律神経の乱れやストレス反応によって引き起こされると考えられており、心の不調が身体にも現れているサインです。
人によっては食欲の低下や睡眠障害、動悸や発汗といった症状が現れることもあります。
こうした身体的な変化は、風邪などの病気と区別がつきにくいため、長引く不調がある場合は適応障害の可能性も念頭に置く必要があるでしょう。
精神面(心)の症状
精神面では、ネガティブな思考が続いたり、気分が落ち込んだ状態が続くことがあります。主に以下のような状態が考えられます。
- 不安感
- 憂うつ
- 焦り
- 些細なことでイライラする
- 緊張感が抜けない
- 心が安定しにくくなる
また、中には自分を責めてしまう気持ちが強まる人もいます。
このような状態になると、日常生活に支障が出る場合もあるでしょう。心の変化は外からは分かりにくく、周囲も本人も気づかないことが多いです。
行動面の症状
行動面では、日常生活の活動に影響が出始め、思ったように行動できなくなることがあります。例えば、以下のようなケースが見られます。
- 学校や職場に行く意欲が失われる(登校拒否・出社困難)
- 感情のコントロールが難しくなる
- 突然涙が出る
- 怒りっぽくなる
- 飲酒や喫煙が増える など
行動の変化は、周囲が比較的気づきやすい特徴でもあるため、家庭や職場での観察が早期発見につながることもあります。
『働くのが怖い』と感じるのも適応障害の特徴
『働くのが怖い』という感覚は、適応障害の典型的なサインのひとつであり、専門的なケアが必要とされる状態です。
「職場に行こうとすると涙が出る」「出勤前に動悸や吐き気がする」など、働くことに対して強い不安や恐怖を感じる場合、適応障害が関係している可能性があります。
職場の人間関係や過剰な業務量、環境の変化などが強いストレスとなり、出勤すること自体が心身への負担になっている可能性が高いです。
このような状態では、無理を重ねることで症状が悪化するおそれがあるため、早めの対応を検討してください。
人によっては「甘えているだけ」と感じて自分を責めてしまうことがありますが、これは甘えではなく病気による反応のため、そのような考えを持つ必要は決してありません。
自分を責めず、治療を進めることについて考えていきましょう。
適応障害の治し方
ここでは、適応障害に対する主な治療法や生活面での工夫について紹介します。
精神療法
適応障害の治療において選択されることが多い精神療法のひとつ『認知行動療法』は、思考の偏りに気づき、ストレスへの感じ方や反応を見直すことで症状の軽減を図る治療法です。
対人関係や職場での課題について、カウンセラーや医師と一緒に整理し、よりよい対処法を見つけることにより、少しずつ回復を目指します。
気持ちが整理され、安心感や自己理解が深まる効果も期待できます。
精神療法は、患者さん一人ひとりの状態に合わせて進められるため、無理なく治療を継続しやすい点も特徴です。
自分のペースで向き合いながら、回復への道筋を探っていきましょう。
薬物療法
状況に応じて、精神療法に薬物療法を併用することもあります。
適応障害で見られる強い不安や不眠、抑うつ気分に効果が期待できる薬を服用し、症状の緩和を目指します。
使用される薬には抗不安薬や抗うつ薬、睡眠薬などがあり、いずれも医師の判断のもとで用いられます。
ただし、薬物療法はあくまで症状の緩和を目的とするものであり、ストレスそのものを解消する手段ではありません。
服薬に対する不安がある場合や、副作用が気になる場合には、遠慮なく医師に相談することをおすすめします。
ラベンダーメンタルクリニック浜松町でも、お薬に関してのご相談が可能な場合がございます。不安がある方はお気軽に医師へお話しください。
環境調整(ストレス原因の除去・軽減)
ストレスの原因になっている環境を見直し、可能な範囲で調整することは、適応障害の改善にとって欠かせません。
例えば、職場での人間関係や業務量に無理がある場合には、配置転換や休職などを検討することも選択肢のひとつです。
学校においても、転校や通学スタイルの変更などで負担を軽減する方法があります。
こうした対応によって、心身にかかるストレスを減らし、症状の緩和を目指します。まずはストレスの原因を特定し、対処の方向性を明確にすることが必要です。
また、本人だけでは解決が難しい場合もあります。その際は医師やカウンセラーと連携しながら必要な手続きを進め、環境改善を図りましょう。
転職
適応障害の原因が職場環境にある場合、転職という選択肢も視野に入れましょう。
環境が変わることによりストレス要因が取り除かれ、症状の改善につながる可能性があります。
特に、パワーハラスメントや過重労働などが原因で心身に不調をきたしている場合には、その環境から距離を置く方法として、転職は有効な考えです。
ただし、焦って転職を進めることは避け、心身の状態がある程度安定してから就職活動を行うほうが望ましいでしょう。
転職活動をスタートする前に、医師やカウンセラーと相談しながら、自分に合った働き方を考えていくことが再発防止にもつながります。
転職は決して『逃げ』ではありません。より健康に働くための前向きな判断です。
生活習慣の見直し
治療や環境調整とあわせて、生活習慣の見直しも適応障害の回復に役立ちます。次項から、心と体の安定を支える基本的な生活習慣を見てみましょう。
バランスの整った食生活
心身の健康を保つうえで、栄養バランスの取れた食事は欠かせません。特に、以下のような栄養素を積極的に摂取するとよいでしょう。
- ビタミンB群(レバー、玄米、豚肉など)
- トリプトファン(バナナ、卵、牛乳、大豆製品など)
- ミネラル(レバー、ほうれん草など)
偏った食生活や不規則な食事は、体調を崩すだけでなく精神面にも影響を与えるため、主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を心がけましょう。
精神的な不調は身体の状態と密接に関係しているため、毎日の食事を整えて体調を維持することは、治療を進める上で大切な習慣です。
適度な運動(有酸素運動)
軽い運動を日常に取り入れることも、心の安定に役立ちます。
運動の習慣はストレス耐性の向上や睡眠の質の改善にもつながり、生活全体の質を高める要素になります。
身体を動かすことで思考が前向きになりやすくなるという側面もあり、医療機関でも運動療法が補助的に取り入れられることは少なくありません。
特に有酸素運動は、気分を落ち着ける神経伝達物質(セロトニン)の分泌を促す効果があり、精神面の改善にも好影響を与えます。
ウォーキングや軽いジョギングなど、無理のない範囲で継続的にできるものを選んでみましょう。
生活リズムを整える
生活のリズムを整えることで、心の落ち着きや集中力の向上が期待され、日々の過ごし方にも前向きな変化が現れやすくなります。
生活のリズムが乱れると自律神経にも影響が出やすくなり、結果として心身のバランスを崩す原因につながりかねません。
毎日決まった時間に起き、朝日を浴びることは、体内時計をリセットするうえで効果的です。
また、昼夜逆転を避けるためには、夜間のスマートフォンの使用を控えるなどの工夫も効果が期待できます。
十分な休養
休養中は『何もしない時間』を意識的に持つことが勧められており、無理に活動しようとするよりも、リラックスを最優先に考えることが回復につながります。
疲れを蓄積させない生活習慣を築くことは、再発の予防にも有効です。
慢性的な疲労や睡眠不足は、症状を悪化させる一因となるため、まずは休むことを優先しましょう。
適応障害の回復の流れ・3つの段階
適応障害の治療は、回復までに段階的なプロセスを踏むことが一般的です。
ここでは、休養期・回復期・調整期という3つの段階について紹介します。
休養期
適応障害の回復において最初に必要とされるのが『休養期』です。この段階では、症状の原因となっているストレスから離れ、心身をしっかりと休めることが主な目的となります。
疲れた心身を十分に休ませることによって、過敏になっていた神経や思考が徐々に落ち着いてくるでしょう。
回復の土台を整える大切な時期として、焦らずゆっくりと過ごしていきましょう。
回復期(リハビリ期)
回復期では、日常生活に徐々に慣れていくことを目標とし、短時間の外出や軽い作業などから少しずつ行動範囲を広げていきます。
突然すべてを元に戻そうとすると再発のリスクが高まるため、無理のないペースを守ることが重要です。
調整期
調整期は、適応障害の症状が和らぎ、日常生活や社会生活への復帰を少しずつ進めていく段階です。
この時期には再発を防ぐための工夫が求められます。例えば、以下のようなことに注目しましょう。
- 趣味などを通じた気分転換
- 深呼吸や瞑想などのリラックス法の活用
- ストレスのサインを早期に察知する習慣を持つ など
家族や職場の理解・協力を得ることで、精神的な負担も軽減されます。
必要に応じて医療機関やカウンセラーと連携しながら、無理なく生活リズムを整えていきましょう。
まとめ
適応障害は、強いストレスによって心身に不調をきたす疾患です。症状や回復の段階には個人差があり、治療には精神療法・薬物療法・生活改善などがあります。
「働くのが怖い」と思う患者さんも多いですが、それは甘えや怠けなどではなく、適応障害という病気の特徴です。落ち込みすぎず、少しずつ治療を進めていきましょう。
ラベンダーメンタルクリニック浜松町では、適応障害で悩む患者さん一人ひとりに寄り添いながら、心身の負担を軽減し、回復を目指すお手伝いをしています。
「適応障害を治したい」「何から始めればいいのか知りたい」など、適応障害に関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。
執筆者
ラベンダーメンタルクリニック浜松町 院長・医学博士
中野 和歌子
- 日本精神神経学会精神科専門医・指導医
- 精神保健指定医
- 産業医科大学産業医学基本講座修了、日本医師会認定産業医
- 日本臨床精神神経薬理学専門医(精神科薬物療法専門医)
- 日本禁煙学会認定専門医
- 臨床研修指導医
- コンサータ処方医登録
- セリンクロ処方医