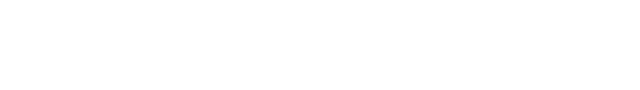うつ病の人への接し方は?禁句や注意点・寄り添い方を解説
うつ病の人と接する際には、言葉の選び方や態度に注意が必要です。何気ない一言が相手を追い詰めたり、寄り添うつもりの言葉が負担になったりすることもあります。
特に、善意からのアドバイスや叱咤激励は逆効果になってしまう場合もあるため、慎重な対応が求められます。
また、身近にうつ病の人がいる時、日常生活の中でどのように寄り添えばよいのか悩む場面もあるでしょう。
相手の気持ちを尊重しながら適切な距離感を保つことが大切であり、その測り方を知っておくと役立ちます。
この記事では、うつ病の人との接し方や避けるべき言葉、日常でのサポート方法について紹介します。うつ病の人への対応に迷っている人は参考になさってください。
うつ病の人への接し方で注意したいこと・やってはいけないこと
うつ病の人と接する際には、言葉の選び方や態度に注意が必要です。励ましや一般的なアドバイスが逆効果になり、相手を追い詰めることもあります。
ここでは、うつ病の人との接し方で避けるべき対応について紹介します。
否定しない
うつ病の人は、自己否定の気持ちが強くなりやすく、周囲の言葉に敏感に反応します。
そのため、「そんなことはない」「気の持ちよう」といった否定的な言葉をかけると、理解されていないと感じ、さらに孤立感が強まる可能性があります。
本人がつらさを訴えたときには、正そうとするのではなく、『つらいと感じているんだね』と気持ちを受け止めてあげましょう。
否定せず、共感する姿勢を示すことで、相手は自己否定や孤立感を強めずに済む可能性が高くなります。
叱咤激励は避ける
「頑張れ」「もっと努力しなきゃ」といった言葉は、うつ病の人にとって大きな負担になることが多いです。
意欲が低下している状態では、頑張りたくても頑張れないため、励ましが逆にプレッシャーになりかねません。
また、「昔はもっとできていたのに」と過去と比較する発言も、自信を失わせる原因になります。大切なのは、無理に励ますよりも相手のペースを尊重し、負担のない範囲で支えることです。
個人的な経験に落とし込まない
うつ病は単なる気分の問題ではなく、脳内神経伝達物質のバランス異常が関与する疾患です。
他人の体験談を受け止めようと思っても、疾患の特徴が原因で対応できず、負担になる恐れがあります。
「私も大変だったけど乗り越えた」「みんなつらいんだよ」といった言葉は、うつ病の人を追い詰めてしまうことが多いです。
自分が大変でも乗り越えられた経験を伝え、励ましたいという気持ちがあったとしても、状況が異なるため、かえって孤独感を強めることになりかねません。
個人の体験を基準にするのではなく、本人の気持ちを尊重し、無理に比較しないようにしましょう。
偏見を持たない
うつ病に対する偏見があると、本人がさらに苦しむ原因になります。
「甘えているだけ」「気の持ちよう」といった固定観念で接すると、理解してもらえないと感じ、誰にも相談できなくなる可能性があります。
また、精神的な病気に対する偏見は、回復を妨げる要因です。
うつ病は特別なものではなく、誰にでも起こりうるものです。偏見をなくし、正しい知識を持つことが、適切な接し方につながります。
うつ病の人に対する禁句・言ってはいけない言葉
うつ病の人に対して、何気なく発した言葉が大きな負担となることがあります。励ましや慰めのつもりでも、相手を追い詰める結果になりかねません。
ここでは、うつ病の人に対して言ってはいけない言葉を紹介します。
「がんばれ」
うつ病の人にとって、「がんばれ」という言葉はとても重いものに感じられます。
頑張りたくても頑張れない状態であるため、この言葉をかけられることでプレッシャーを感じ、自分を責める原因になりかねません。
特に、すでに十分努力している場合、さらなる負担を与えることになります。
励ましたい気持ちがあったとしても、無理に背中を押すのではなく、「大変だったね」「つらかったね」と気持ちを受け止める姿勢が求められます。
「気にしすぎ」
「気にしすぎ」という言葉は、本人の悩みを軽視しているように受け取られる恐れがあります。
うつ病の人は、考えすぎることで不安やストレスを強く感じやすい状態にありますが、この言葉をかけると自分の悩みが取るに足らないものだと感じ、さらに孤独を深めることになりかねません。
「そんなに気にしなくてもいいのに…」と思っても、「つらいと感じているんだね」と共感する姿勢を示したほうがよいでしょう。
「甘えないで」
うつ病の人に「甘えないで」という言葉をかけると、病気に対する理解がないと感じさせてしまうことがあります。
気持ちの持ち方だけで回復するものではないため、こうした言葉は相手をさらに追い詰める原因になります。
うつ病は単なる気分の問題ではなく、脳の働きが関係している疾患です。本人の気持ちだけでは対応できないことがあると理解しましょう。
「無理しないで」
「無理しないで」という言葉は、一見すると相手を気遣う表現に思えます。
しかし、うつ病の人にとっては、「無理しないとやって生きていけないのに」と感じるきっかけになることがあります。
また、「どうすればいいのか分からない」と混乱を招き、具合を悪化させてしまう恐れもあるでしょう。
どうしても言葉をかける必要がある時には、具体的な内容を伝えてみる方法も大切です。
相手に寄り添う時には、言葉の内容だけでなく、伝え方やタイミングにも注意を払いましょう。
「会社はどうするの」
仕事をしているうつ病の人に対して、「会社はどうするの」と尋ねると、大きなストレスを与えかねません。
仕事に関する話題を出されると、焦りや罪悪感が強まり、さらに追い詰められる原因になるでしょう。
仕事を続けたいという気持ちがあっても、体が思うように動かない状態が続く場合があります。まずは相手の体調を優先し、「今は休むことが大事だよ」と伝えることが大切です。
すぐに決断を求めるのではなく、状況が落ち着くまで見守る姿勢を持つと、本人の負担を軽減しやすくなります。
「心を強く持って」
「心を強く持って」という言葉は、うつ病の人にとってプレッシャーになります。
病気によって気力が低下している状態では、気持ちを強く持つこと自体が難しく、無理に頑張ろうとするとかえって症状が悪化する可能性もあります。
相手が安心できるように、無理に励まさず、気持ちを受け止める姿勢を意識してみてください。
「私だって大変なのに」
「私だって大変なのに」という言葉は、相手のつらさを軽視していると受け取られる可能性があります。
うつ病の人は、自分の状態を理解してもらえないと感じるとさらに孤立してしまいます。
また、「自分よりも他の人のほうが大変なのかもしれない」と考え、悩みを誰にも打ち明けられなくなることもあるでしょう。
相手を責めるのではなく、「つらいんだね」と共感する姿勢が大切です。比較せず、相手の気持ちをそのまま受け止めることで、安心感が生まれ、心を開きやすくなります。
「本当にうつ病なの?」
「本当にうつ病なの?」という言葉は、病気の深刻さを軽視している印象を与え、うつ病の人を深く傷付ける恐れがあります。
うつ病の症状は人それぞれで、外見からは分かりにくい場合もあります。しかし、見た目に関係なく、本人が苦しんでいる事実を受け入れることが重要です。
不安や苦しみを抱えている人に対しては、否定せず、安心できる環境を整えられるように接しましょう。
うつ病の人に対する生活の中での寄り添い方
うつ病の人と生活する際には、特別な対応をするよりも、日常生活の中での自然な関わりが大切です。
ここでは、身近な立場の人が意識したい寄り添い方について紹介します。
本人が一番焦っていることを理解する
うつ病の人は、自分が周囲に迷惑をかけているという思いから、強い焦りや罪悪感を抱えていることが少なくありません。
そのため、無理に気持ちを切り替えさせようとせず、「つらいよね」「今はゆっくり休もう」と、感情に寄り添った言葉をかけるほうが安心感につながるでしょう。
特別扱いしない
うつ病の人を必要以上に気遣いすぎると、自分は普通ではないという印象を持たせてしまうことがあります。
特別扱いされることで、かえって劣等感や疎外感を強めてしまうケースもあるため注意が必要です。
無理をさせないことは前提としつつも、あくまで対等な関係として接することで、相手に安心感を与えられます。
無理に励まさない
うつ病の人に対して「頑張って」「元気出して」といった励ましの言葉をかけると、気遣いのつもりでも逆効果になることがあります。
意欲が低下している状態では、前向きな言葉が重荷になり、自責の念を強める原因になることもあるでしょう。
周囲の期待に応えられないことに苦しんでいる場合もあるため、励ましではなく、自然に安心できて落ち着いた時間を過ごせる環境を整えるほうが精神的な支えになります。
服薬管理を手伝う
家族や周囲の人がさりげなく服薬の確認をしたり、タイミングを一緒に見守ったりしてあげましょう。
うつ状態が重い時期には、服薬を忘れたり、やめたくなったりする場合もあります。しかし、うつ病の治療には、医師から処方された薬を継続して服用することがとても大切です。
飲み忘れていた時には強く言うのではなく、「薬飲んだ?」と優しく聞いてあげるとよいでしょう。
再発に注意する
回復後も無理をせず、日常の中でストレスを減らす工夫を取り入れることが大切です。
うつ病は再発率の高い病気として知られています。症状が改善したように見えても、本人が無理を重ねたり、周囲が元の生活を求めたりすると、再び悪化する可能性があります。
感情の起伏が激しくなったり、疲労感を見せるようになったりした場合は、再発の兆候である可能性があるため、注意深く見守りましょう。
うつ病の自殺のサインを見逃さないで
うつ病の人が自殺を考えている場合、周囲に何らかのサインを発していることがあります。
ここでは、うつ病の人が発するサインやその対応方法について紹介します。
話を逸らさない
うつ病の人が「消えたい」「もう疲れた」などの言葉を口にすることがあります。このような発言を聞いたとき、聞き流さず、真剣に耳を傾けることが重要です。
「そんなふうに思っているんだね」と受け止める姿勢を示すことで、安心感を与えやすくなります。
じっくり聞いてあげる
うつ病の人が自殺について話し始めたとき、無理に説得しようとすると逆効果になることがあります。
「つらいんだね」と受け止め、安心して話せる環境を作り、じっくり話を聞いてあげましょう。
感情を抑え込むのではなく、言葉にすることで気持ちが整理されることもあります。
治療を勧めてみる
うつ病の人が自殺を考えているとき、専門的な治療が必要なことが多いですが、本人が治療に消極的なことも少なくありません。
このような場合、周囲は決して強制せず、本人の気持ちを尊重する姿勢が望ましいでしょう。
「一緒に相談してみない?」「話を聞いてもらうだけでも」など、優しく提案してあげてください。治療に対するハードルが下がり、受診しやすくなるかもしれません。
支える人のケアも必要
支える側の心のケアも、長期的なサポートには欠かせません。
うつ病の人を支える家族や友人も、精神的に大きな負担を抱えることがあります。相手を気遣うあまり、自分自身の疲れやストレスを見過ごしてしまうこともあるでしょう。
しかし、支える側の心がすり減ってしまうと、適切なサポートが難しくなることもあります。必要に応じてカウンセリングを受けたり、信頼できる人に相談したりすることも大切です。
まとめ
うつ病の人への接し方は、何気ない言葉や態度が大きな影響を与えるため、慎重に考える必要があります。
「がんばれ」などの励ましや否定的な言葉は避け、相手の気持ちを尊重する姿勢が大切です。話を聞く時にはじっくり耳を傾け、安心して過ごせる環境を整えてあげましょう。
また、うつ病の人を支える側も無理をせず、自分自身の心のケアも意識してください。
ラベンダーメンタルクリニック浜松町では、うつ病の人だけではなく、ご本人を支えるご家族、周囲の人へのケアも同時に心がけています。
うつ病の人を長くサポートし続けていてつらい、適切なサポートの仕方が分からない…などのお悩みもご相談いただけますので、気になることがあればどうぞお気軽にご連絡ください。
執筆者
ラベンダーメンタルクリニック浜松町 院長・医学博士
中野 和歌子
- 日本精神神経学会精神科専門医・指導医
- 精神保健指定医
- 産業医科大学産業医学基本講座修了、日本医師会認定産業医
- 日本臨床精神神経薬理学専門医(精神科薬物療法専門医)
- 日本禁煙学会認定専門医
- 臨床研修指導医
- コンサータ処方医登録
- セリンクロ処方医
- 電車でお越しの場合
浜松町駅北口から徒歩2分 - 地下鉄でお越しの場合
大門駅B5出口直結 - バスでお越しの場合
都営バス大門駅1番乗り場、3番 乗り場から徒歩2分