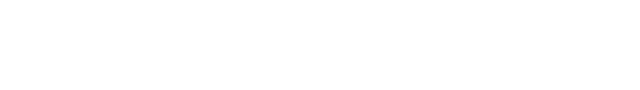人の話を聞かないのは認知症の初期症状?原因・対処法・向き合い方を紹介
認知症の人と接していると「人の話を聞かなくなった」と感じることがあります。
認知機能の低下や性格の変化によって人の発言に聞く耳を持たなくなったり、自分の話を一方的にしたりするケースがあるため、認知症の人と会話をする際は話し方・聞き方に注意が必要です。
では実際は、どのように会話をすることが理想なのでしょうか。
この記事では、認知症の人が話を聞かなくなる理由やそう思われる原因、上手にコミュニケーションをとる方法を紹介します。
認知症の初期症状には個人差があるため、会話に違和感が生じた場合や、家族に疑わしい変化がみられた場合は参考にしてください。
認知症になると人の話を聞かなくなる?
知症になると、会話が上手く成立しなくなったり話したことをすぐに忘れてしまったりすることで「人の話を聞いていない」と感じることがあります。
認知症では理解力や判断力が低下するため、相手の話を聞いてもピンとこず反応が鈍くなることで話を聞いていないように感じるケースがあります。
また自分の話を聞いてほしい意識が強くなって一方的に話したり、短気になって聞く耳を持たなくなったりするケースも多いです。
認知症の人ではもの忘れが増えますが、プライドや自尊心が高くなる傾向があるため、上手く会話ができないことを咎めると、その記憶だけ残る場合があります。
その結果、会話拒否や反抗的な態度につながる恐れがあるため、上手くコミュニケーションをとることで円満に会話をする工夫が必要です。
認知症の初期症状
認知症には以下の初期症状がみられるため、当てはまる場合は早めに医療機関を受診しましょう。
- 人の話を聞かなくなった
- 最近の出来事を忘れやすくなった
- 短気になった
- 複数のことを同時に行えなくなった
- 趣味や娯楽への興味が薄れてきた
- 身だしなみへの関心がなくなってきた
- 言い訳や嘘が増えた
- 食事を忘れる、または頻度が増えた
- 集中力が続かなくなった
- 日付や時間の感覚が分からなくなる
認知症の初期症状には、人の話を聞かなくなるほかにも、忘れっぽくなる、性格が変わる、物事を順序だてて行えなくなるなどさまざまなものがあります。
最初のうちは生活に大きな影響を及ぼすほどの症状ではなく、家族や友人など周囲の人がいつもと違う状態に違和感を感じて発覚するケースが多いです。
認知症には原因によっていくつかの種類があるため、人によって症状が異なります。
認知症にみられる忘れっぽさは、いわゆるド忘れのような状態ではなく出来事そのものを忘れてしまう状態で、頻度が増えたら要注意です。
また初期の認知症では、よく怒るようになったり言い訳や噓が増えたりするケースが多く、認知症の症状によるものもあれば、自身が認知症だと認めたくない感情から現れる態度であるケースもあります。
一般的に認知症は完治が出来ず、治療によって進行を遅らせたり症状を緩和したりする対処が選択されます。
ただし、種類によっては外科手術で完治が可能なケース(慢性硬膜下血腫、脳腫瘍、正常圧水頭症など)もあるため、違和感を感じたら早めに医療機関を受診しましょう。
認知症の人が話を聞かないのはなぜ?
認知症の人は、以下の特徴から人の話を聞かなくなる可能性があります。
自分が正しいという思考が強いため
認知症になると、プライドが高くなることで自分が正しいという思考が強くなり、人の話を聞かなくなるケースがあります。
自制心が正常に機能していればプライドが傷つく出来事があってもある程度の我慢が出来ますが、認知症になると感情のコントロールが難しくなり、自分の思い通りにならないことに強い不満を感じやすいです。
周りが正しくて自分が間違っていることを認めたくない気持ちが強く働くため、聞く耳を持たず話を聞いてくれない原因になります。
また認知症ではこだわりが強くなることも症状の一つであるため、一度相手が間違えたと決めつけるとその後いくら説明されても理解が難しく、介護者や家族の心の負担も大きくなります。
自分の話をしたい気持ちが強くなるため
認知症になると、自分の話を相手に伝えなければという責任感が強くなるため、一方的に話すことが増える傾向があります。
特に高齢の方の場合は長く生きてきたことで物知りの人が多く、最近の出来事を忘れても過去の記憶は残っているケースが多いです。
そのため、自分の知っていることを教えてあげないと、という意思が強くなりよく喋るようになります。
人の話を理解するのが難しい状態で自分の話を相手に伝えることに夢中になるため、話を聞かない印象を持たれます。
不安やストレスから発言量が増えるため
認知症になると不安やストレスを感じやすくなり、それが原因でよく喋るようになるため一方的に話していると捉えられるケースがあります。
自分の記憶力や理解力の低下に不安を感じたり、ストレスを受けたりすると、たくさん話すことで安心感を得ようとします。
うまくコミュニケーションをとることで相手の内心を理解し、不安が解消できるように努めましょう。
認知症の人が話を聞いていないと感じる原因
認知症の人には以下の苦悩があるため、周囲の人に話を聞いていないと感じさせてしまう可能性があります。
言われていることの理解が難しいため
認知症では理解力や判断力が低下するため、相手が話していることを理解できずに話を聞いていないと思われる場合があります。
「お出かけしようね」「お風呂に入ろうね」という言葉の意味自体が理解できなかったり、そのためには何をしたらいいのかが分からなかったりします。
例えば出かけるための説明は、服を着替える・靴を履く・車に乗るなどの動作を一つずつ促す工夫が必要です。
話したことを忘れてしまうため
認知症には最近の出来事が記憶から抜け落ちる特徴があるため、話したことをすぐに忘れてしまうケースがあります。
「あとでお薬を飲んでね」と話しても、その時になるとお願いされたこと自体を忘れている可能性が高いです。
また理解力や判断力が低下するため、「お昼になったら声をかけてね」と話しても、誰からお願いされたかを忘れてしまったり、直後に声をかけてきたりするケースもあります。
そのため、何か要求がある場合は行動してほしいタイミングでその都度話すことが大切です。
会話がかみ合わないため
認知症では言われたことを理解する能力が低下し、自分の意思を言葉にするのが難しくなるため、会話がかみ合わなくなり話を聞いていないように感じてしまいます。
認知症の人との会話では、同じことの繰り返しや矛盾・妄想を含んだ内容の発言がみられます。
また相手の発言の意図が汲み取れなかったり、自分の主張を優先したい気持ちが強かったりするため、話の辻褄が合わなくなるケースも多いです。
その結果、会話が一方的だ・こちらの話を聞く気がないといったイメージを受けます。
同時に複数の情報を処理できないため
認知症では頭で情報を処理する能力が低下するため、同時に複数の話をされると理解が出来ず話を聞いてないように見えるケースがあります。
例えば、「ご飯を食べてからお薬を飲みましょうね」と話しても、ご飯を食べる動作と薬を飲むという動作を同時に理解するのが困難なため、どちらかの行動が疎かになる可能性があります。
本人は、ご飯を食べる・薬を飲むという指示を守っているつもりでも、言った人の目線では話を聞いていないと感じるでしょう。
認知症の人と上手く会話するための対処法
認知症の人は記憶力や理解力が低下することで話を聞いていないように感じるケースがありますが、それによって叱ったり大声を出したりすると信頼関係に悪影響を及ぼします。
相手が自信をなくさないよう、以下の点に注意してコミュニケーションをとりましょう。
短い言葉で分かりやすく話す
認知症の人と話すときは、言葉を短く区切って分かりやすく話すことが大切です。
認知症の人は、一つの発言にいくつもの言葉が入っているとそれらの情報をすべて処理しなければいけないと思い混乱します。
「ご飯を食べてお薬を飲んでからお出掛けしましょうね」と一続きに話すのではなく、「ご飯を食べてね」「お薬を飲んでね」「お出掛けをしようね」と区切って説明するのが望ましいです。
また、聞き取りやすい声量でゆっくり話すことも大切です。
耳が聞こえにくい人を相手にしている場合は大きな声で話す必要がありますが、怒っている口調にならないように、柔らかい言葉遣いを心掛けましょう。
相手の表情も気にかける
認知症の人と会話をするときは、表情にも目を向けるようにしましょう。
眉間にしわを寄せていたり暗い表情をしていたりする場合は、話していることが理解できていない可能性があるため、そのまま会話を続けると混乱してしまいます。
普段から表情があまり変わらない人の場合は、声のトーンを観察するのも効果的です。
また、高い視点から話しかけることで、見下されていると感じる認知症の人もいます。
そのため、認知症の人と話すときは目線を合わせ、寄り添った対応を心掛けましょう。
発言を否定せずに聞く
認知症になると間違った発言をするケースが増えますが、否定せずに寄り添った姿勢で耳を傾けましょう。
認知症の人への対応で大切なことは、間違いを正すことではなく、相手を尊重して発言を受け入れることです。
自分の言い分を否定されることで、自信の喪失やストレスにつながる可能性があります。
妄想や虚言があっても、「大丈夫です」「もう安心ですよ」など、落ち着きを取り戻せるような工夫をしましょう。
相手の話すペースを尊重する
認知症の人と会話する際は、発言を急かしたり遮ったりせずに話すペースを尊重してあげましょう。
発言を遮ったり途中で質問攻めにしたりすると、混乱して余計に時間がかかる可能性があります。
上手く言葉にできずに、同じことを何回も話したり言葉に詰まったりする可能性がありますが、本人のペースに任せることが大切です。
また会話だけではなく行動をする際も、急かすことで怪我につながる恐れがあります。
「待っていますので大丈夫ですよ」「ゆっくりで問題はないですよ」などの声掛けをしてあげると、焦る必要がないという安心感につながり、会話が円滑に進むでしょう。
身振りや手振りを交える
大きな声でゆっくり話すほかに、身振りや手振りを交えて会話をすることが推奨されます。
言葉には具体的な形がなく、認知症の人にとっては理解が難しい可能性があるため、視覚で認識できるジェスチャーを取り入れて会話をしましょう。
手を洗う・ご飯を食べるなどの動作のほか、腕につかまる・手すりにつかまるなどの行為は、実際につかんで見せたり手でトントンと叩いて場所を示したりするのが効果的です。
スキンシップを取りながら話を聞く
認知症の人と会話をする場合は、スキンシップを交えてコミュニケーションをとりましょう。
手を握ったり背中をさすったりすると、温もりを感じることで気持ちが穏やかになり落ち着いた状態で会話ができます。
また、触れられた感覚と記憶が結びつき、会話の内容を覚えやすくなります。
ただし、人によっては他人に触れられることを嫌がるケースがあるため、相手の反応や表情を観察しながら取り入れましょう。
まとめ
認知症で人の話を聞かなくなる原因や、上手なコミュニケーションの方法を紹介しました。
相手にとっては話を聞いていないつもりはなく、理解できないことで苦しんだり自分で間違ったことを言っている自覚がなかったりするケースが多いです。
認知症の人との会話では内容がかみ合わなかったり、話がなかなか進まなかったりしますが、相手の発言を尊重し、受け身になって聞くことを意識しましょう。
ラベンダーメンタルクリニック浜松町は、浜松町駅から徒歩2分、大門駅B5出口直結の位置にある精神科・心療内科クリニックです。
精神科薬物療法専門医の資格を持つ女性医師が、認知症の患者さん一人ひとりの心身の不調に合わせたきめ細かな治療・サポートを行います。
患者さんの特性や症状に合わせてオーダーメイドの治療や支援を提供するため、認知症の初期症状がある方や、ご家族に認知症の初期症状の疑いがある方は一度お気軽にご相談ください。
執筆者
ラベンダーメンタルクリニック浜松町 院長・医学博士
中野 和歌子
- 日本精神神経学会精神科専門医・指導医
- 精神保健指定医
- 産業医科大学産業医学基本講座修了、日本医師会認定産業医
- 日本臨床精神神経薬理学専門医(精神科薬物療法専門医)
- 日本禁煙学会認定専門医
- 臨床研修指導医
- コンサータ処方医登録
- セリンクロ処方医
- 電車でお越しの場合
浜松町駅北口から徒歩2分 - 地下鉄でお越しの場合
大門駅B5出口直結 - バスでお越しの場合
都営バス大門駅1番乗り場、3番 乗り場から徒歩2分