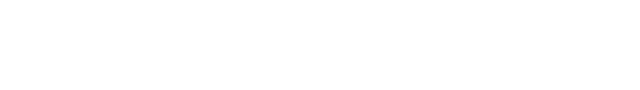PMS治療は婦人科と心療内科のどっちに行くべき?受診目安や選び方
PMS(月経前症候群)の症状は、身体的な不調だけでなく、気分の落ち込みやイライラなど精神的な影響も伴います。そのため、治療を考えた際に、婦人科と心療内科のどちらを受診すべきか迷う人も少なくありません。
PMSの治療は症状に応じて適切な診療科を選ぶことが大切で、場合によっては両方の受診が必要になることもあります。
この記事では、心療内科と婦人科の治療の違いや、受診の目安、PMSをコントロールする方法について紹介します。
適切な医療機関を選び、PMSの症状を和らげる効果的な治療を受けるための参考になさってください。
PMSの治療は心療内科と婦人科のどっちを受診すべき?
PMS(月経前症候群)の治療を受ける際、心療内科と婦人科のどちらを選ぶべきか迷う人も多いでしょう。
治療方法は症状の種類や程度によって異なるため、適切な診療科を選ぶことが重要です。
ここでは、心療内科と婦人科の治療法の違いを紹介し、受診の目安について解説します。
心療内科の治療法
PMSの症状が主に精神的なものである場合、心療内科での治療が推奨されます。
例えば、気分の落ち込みやイライラ、不安感が強く、日常生活に支障をきたしている場合、心療内科で抗うつ薬や抗不安薬の処方が検討される可能性が高いです。
このような薬は脳内の神経伝達物質のバランスを整える効果があり、症状の改善に役立ちます。
また、認知行動療法などのカウンセリングを通じて、ストレス対処法や考え方のクセを見直すサポートを受けられる点も特徴です。
特に、PMSによる感情の波が大きく、対人関係や仕事に悪影響が出ている場合は、専門家のアドバイスを受け、適切な対処法を学ぶことも大切です。
ただし、PMSの原因がホルモンバランスの乱れにあれば、心療内科の治療だけでは十分な改善が見込めない可能性もあります。
そのため、婦人科との連携を考慮しながら治療方針を決めることが重要です。
婦人科の治療法
PMSの主な原因はホルモンバランスの変化とされており、その影響が強い場合、婦人科ではこれを調整する治療が中心となります。
低用量ピル(経口避妊薬)を用いてホルモンの変動を安定させる方法が一般的で、PMSの症状が軽減される可能性があります。
婦人科では、PMSが更年期障害や子宮内膜症といった他の婦人科疾患と関連していないかを確認することも可能です。
特に、生理周期の乱れや月経痛が強い場合は、婦人科での診察が推奨されます。
症状によっては両方の受診も視野に
PMSの症状は多岐にわたるため、精神的・身体的な不調がどちらも強く現れる場合は、心療内科と婦人科の両方の受診もおすすめです。
例えば、ホルモン治療によって身体的な症状が改善しても、気分の落ち込みやイライラが残る場合、心療内科でのカウンセリングや薬物療法を併用することで、よりよい改善が期待できます。
また、PMSの症状がPMDD(月経前不快気分障害)に発展している場合、心療内科での診断と治療が不可欠です。
PMDDはPMSよりも精神症状が重く、日常生活に大きな影響を及ぼす可能性があるため、適切な診断を受けることが重要です。
自分の症状がどちらの診療科なのか判断がつかない場合は、まず心療内科か婦人科のどちらかを受診し、必要に応じて適切な科を紹介してもらうという方法もあるため、迷ったらまずは受診を検討しましょう。
医療機関を受診する目安
PMSの症状が軽度であり、日常生活に大きな影響を及ぼさない場合は、生活習慣の見直しや市販薬の使用で対応できることもあります。
しかし以下のようなケースでは、生活への悪影響が心配されるため、医療機関の受診を検討したほうがよいでしょう。
- PMSの症状が毎月強く現れ、生活に支障をきたしている
- 気分の落ち込みや不安感が強い
- 生理前後の症状が極端に重く、うつ状態に近い
- 体調不良が続き、ほかの疾患が関与している可能性がある
このような状態が続く場合、心療内科または婦人科の受診を検討し、適切な治療を受けることが大切です。
PMSは放置すると症状が悪化する可能性もあるため、早めの対応をおすすめします。
PMSで医療機関を受診する目安
PMS(月経前症候群)の症状が重く、日常生活に影響がある場合は、早めに婦人科や心療内科を受診し、自分に合った治療方法を見つけることが重要です。
軽度の症状であれば生活習慣の見直しやセルフケアで改善することもありますが、強い不調が続く場合は専門医による診察が必要です。
特に、気分の落ち込みやイライラが激しく、人間関係や仕事に影響を及ぼしている自覚があれば、早めに病院を受診してください。
また、頭痛や腹痛、吐き気、めまいなどの身体的な症状がつらい場合も、医師の診察を受けることで適切な治療が受けられます。
自己判断で放置すると、症状が悪化してPMDDへ移行する可能性もあります。
こんな症状はPMSを疑うべき
PMS(月経前症候群)では、心や体にさまざまな不調が現れることがありますが、症状の種類や程度は個人差が大きいのが特徴です。
ここでは、PMSによる心や体の不調、PMS以外が原因となるケースについて紹介します。
心に不調が起こる
PMSでは、月経前に気分の落ち込みやイライラ、不安感が強まることがあります。普段は気にならないことでも過剰に反応してしまい、感情のコントロールが難しくなる時もあるでしょう。
また、集中力の低下や無気力感が続く場合、日常生活や仕事に影響を与える可能性が高まります。
特に、些細なことで涙が出たり、強い不安を感じたりするようになった場合は、PMSの影響が疑われます。
月経が始まると症状が軽減する特徴があるため、自身の状態を記録しながら状態を把握し、対策を取るのもおすすめです。
身体に不調が起こる
PMSの症状には、身体的な不調も含まれます。頭痛や腹痛、腰の痛みなどをはじめ、以下のような症状がある場合、PMSの可能性があります。
- 頭痛
- 腹痛
- 腰痛
- むくみ
- 乳房の張り
- 吐き気やめまい
- 便秘・下痢 など
このほか、疲労感や倦怠感が抜けず、活動が制限されるケースも少なくありません。
このような症状が強く現れ、日常生活に支障を感じる際は、婦人科や心療内科で相談してください。
PMS以外が原因のことも
PMSの症状と似た不調には、PMDD(月経前不快気分障害)や月経困難症などが含まれます。
PMDDはPMSよりも精神的な症状が重く、抑うつ感や強い怒りを伴うことが多いです。
月経困難症は生理痛が特に強く、日常生活に大きな支障をきたす状態を指します。
いずれの場合も適切な治療を受けることで症状の軽減が期待できるため、我慢せずに受診を検討しましょう。
PMSを上手にコントロールする方法
PMSの症状を和らげるためには、心療内科や婦人科での治療を受けながら、日常生活の習慣を見直すことも重要です。
生活習慣の改善によって症状が軽減されるケースも多く、適度な運動や食事の工夫などが有効とされています。
ここでは、PMSのコントロールに役立つ具体的な方法を紹介します。
適度な運動
適度な運動は自律神経のバランスを整えたり、ストレス解消になったりする効果があり、PMSの症状軽減が期待できます。例えば、以下のような運動がおすすめです。
- ウォーキング
- ストレッチ
- ヨガ など
このような軽い運動は血行を促進し、自律神経のバランスを整える助けになります。また、ストレスの解消にもつながるため、気分の落ち込みやイライラを和らげる効果が期待できるでしょう。
運動を継続することでホルモンバランスが安定し、PMSの予防にもつながります。無理のない範囲でできる運動を取り入れて、PMSの症状を和らげる工夫をしましょう。
飲酒や過度な塩分を控える
アルコールや塩分の摂取量を見直し、バランスの取れた食生活を心がけることも、PMSの症状を軽減させるコツのひとつです。
アルコールの摂取はPMSの症状を悪化させる要因で、血糖値の急激な変動を引き起こし、気分の不安定さを助長することがあります。
また、塩分の過剰摂取は水分バランスを崩し、むくみや頭痛を引き起こすため、控えるのが望ましいでしょう。
過度の飲酒を控え、加工食品やスナック菓子、塩分の多い調味料を避けるなど、日常生活の中で改善しやすいものから取り入れていきましょう。
禁煙する
喫煙習慣がある人は、少しずつ本数を減らすことを意識するとよいでしょう。
喫煙は血流を悪化させ、自律神経の乱れを引き起こす要因になったり、煙草に含まれているニコチンが血管を収縮させ、冷えやむくみを悪化させたりする可能性が高いです。
また、ホルモンバランスに影響を与え、月経周期が乱れる原因にもなります。
このような影響により、PMSの症状が悪化する恐れがあるため、禁煙を検討するのもおすすめです。生活習慣の見直しとともに、禁煙に挑戦してみてはいかがでしょうか。
栄養バランスの見直し
PMSの症状を和らげるためには、栄養バランスの取れた食事が重要です。カルシウムやマグネシウム、ビタミンB群は精神の安定やホルモンバランスの調整に役立ちます。
例えば、ナッツ類や葉物野菜、魚介類などを意識的に摂取するとよいでしょう。
また、精製された糖質を控え、食物繊維の多い食品を選ぶのも効果的です。
PMSの患者さんは糖質を多く摂取しているケースが多く、その影響でビタミンB群を消費してしまい、PMSの症状に悪影響を与えている可能性があるためです。
PMSの影響を抑えるためには、食事内容を見直し、必要な栄養素を適切に補うことが大切になります。
PMSダイアリーをつけてみる
PMSの症状を理解し、適切に対処するためには、自身の体調の変化を記録することも効果的です。
PMSダイアリーをつけることで、症状のパターンを把握しやすくなり、医療機関での診察にも役立つでしょう。
以下のような項目を記録してみてください。
- 月経の開始日
- 終了日
- 気分の変化
- 体調の変化
- 食事内容 など
PMSダイアリーの記録を追えば、症状が特に強い日や、生活習慣とPMSの関係を把握できるため、症状軽減に役立つ適切な対策を講じやすくなるでしょう。
PMSを放置するとどうなる?
PMSを放置すると、周囲との関係性に悪影響が生じたり、症状が悪化してPMDD(月経前不快気分障害)へと進行したりするリスクがあります。
ここでは、PMSを放置することで生じる主な影響について紹介します。
人間関係や仕事への悪影響
PMSの影響で気分の浮き沈みが激しくなると、周囲との関係が悪化する原因になることがあります。
感情のコントロールが難しくなると、無意識のうちに攻撃的な言動を取ってしまうこともあり、人間関係に悪影響を及ぼします。
また、集中力の低下や疲労感が強くなることで、仕事の効率も落ちる恐れがあります。ミスが増えたり、作業に時間がかかったりすると、職場での評価が下がる可能性もあるでしょう。
このような問題が続くと、精神的な負担が増し、ストレスがさらに強くなる悪循環に陥ることも考えられます。
PMDD(月経前不快気分障害)になる可能性
PMSを放置すると、より深刻な症状を伴うPMDD(月経前不快気分障害)に進行する可能性があります。
PMDDはPMSよりも精神的な症状が重く、強い抑うつ感や怒り、不安感が特徴です。
PMDDの症状が現れると、気分の落ち込みが激しくなり、対人関係に支障が生じるだけでなく、自分自身を否定的に捉えることが増えることもあり、精神的な負担がさらに大きくなります。
PMSの段階で症状の悪化を防ぐためにも、早めの対策が重要です。症状が強く出ている場合には、我慢せずに婦人科や心療内科で相談し、適切な治療を受けることを強くおすすめします。
まとめ
PMSの症状は心身にさまざまな影響を及ぼし、日常生活や人間関係に悪影響を与えることがあります。
適切な治療を受けずに放置すると、症状が悪化し、PMDDへ進行する可能性もあるため、早めの対策が重要です。
婦人科や心療内科を受診し、自分の症状に合った治療を受けることで、PMSの影響を軽減しやすくなります。症状が強く、生活に支障を感じる場合には、専門医に相談しながら適切な対処を進めていきましょう。
ラベンダーメンタルクリニック浜松町では、PMS症状についてのお悩みに対応可能です。婦人科か心療内科のどちらを受診するべきか迷っている場合でも診察し、適した科をご案内します。
「PMSによる心身への負担を軽減したい」「適切な治療を受けたい」というご希望があれば、お気軽に当院へお越しください。
執筆者
ラベンダーメンタルクリニック浜松町 院長・医学博士
中野 和歌子
- 日本精神神経学会精神科専門医・指導医
- 精神保健指定医
- 産業医科大学産業医学基本講座修了、日本医師会認定産業医
- 日本臨床精神神経薬理学専門医(精神科薬物療法専門医)
- 日本禁煙学会認定専門医
- 臨床研修指導医
- コンサータ処方医登録
- セリンクロ処方医
- 電車でお越しの場合
浜松町駅北口から徒歩2分 - 地下鉄でお越しの場合
大門駅B5出口直結 - バスでお越しの場合
都営バス大門駅1番乗り場、3番 乗り場から徒歩2分